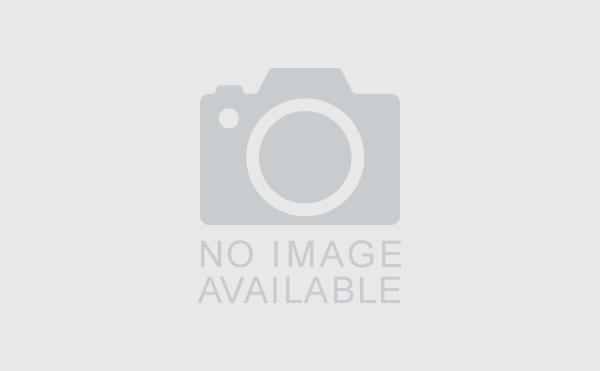大切な力②~書く力
下妻市内の小学校では,明日から3学期が始まります。
今週末に「茨城県学力診断のためのテスト」があるので,ゆっくり新年や新学期の始まりを味わっている時間はないかもしれません。それでも,早々に「新年の抱負」や「新学期のめあて」などを書くことでしょう。
学校では,「書く」機会がたくさんあります。
漢字の読み方は,ひらがなで書きます。
(例:新年→しんねん)
大きな数の読み方は,漢数字で書きます。
(例:39856→三万九千八百五十六)
自分の考えも,ノートやプリントに書きます。
読めるか,どんなことを考えたか,ということも,一斉授業のなかでは書いて表現して伝えることが多いのです。
もちろん,各教科の授業で学んだ記録は,ノートなどに書き残します。
家庭学習も,プリントやノートに書いて提出します。
ドリル学習のように,覚えるまで何度も書いて練習するものもあります。
各教科のテストも,書いて答えますね。
書くことが苦手な子にとって,学校の学習は,とても面倒で嫌なものになりがちです。本格的にノートに書き始める1年生の5月後半から,登校をしぶりだす子がいます。高学年になって,みんながノートを書いているときに机に伏せて寝ている子がいます。
また,指導する側としても,「書かない」のか「書けない」のか判断しづらく,指導が遅れてしまうことがあります。
例えば,漢字練習の際に「読み仮名」を書かない子がいます。たいていの場合,書くことが嫌いな子です。漢字のノートには,しばしば先生から赤ペンで「読みがなも書きましょう。」などと書かれています。そして,漢字テストでは,漢字も書けないし,読み方も書けなかったりまちがえていたりします。そんな子に漢字ドリルを音読させてみたら,実は全く読めなかった,ということがありました。
書くことが嫌い
↓
漢字はドリルを見て真似して書く(面倒・苦痛,とりあえず宿題だから)
↓
読みがなは書かなくてもいいだろう(とっても面倒,読みがなは書かなくても許されるかも…)
↓
何度練習しても,読み方も意味も分からない漢字を写しているだけ(覚えられるはずがない!記号を書き写しているのと同じ!)
↓
我慢してやっているのに,どんどん分からなくなり,ますます嫌いになる
この子には,読みがなは無理に書かせず,自分が書いてきた漢字ノートをこっそり音読させて,読めなかった漢字にだけその場で読み仮名を書かせるようにしました。すると,次の漢字テストでは,「漢字の読み」がほとんどできただけでなく,「漢字の書き」も以前よりもたくさん正解することができるようになりました。すると,漢字練習に対する学習意欲がわいてきて,自分から読みがなをつけてくることも増えてきました。
この子のように,周りも本人も「書かない」と思っていることが,実は「書けない」場合があります。
「書くこと」が苦手なのには,いろいろな原因が考えられます。
鉛筆の持ち方が原因だった子もいます。
見え方に困難を抱えていた子もいます。
姿勢を保つことが苦痛だった子もいます。
「どうしてやらないの!」と叱責する前に,「書きたがらないのは,なぜなのかな?」という視点で,お子さんの様子をご覧になってみてほしいと思います。お子さん自身が一番嫌な思いをしているはずです。
「書く力」は,学校生活では多用される大切な力ですが,人が持つたくさんの能力の中の一つに過ぎません。その一つのために,自信を失ってしまったり勉強が嫌いになってしまったりしないように,正しい対応をしていきたいものです。
本塾では,書く力を高める指導も行っております。お気軽にご相談ください。