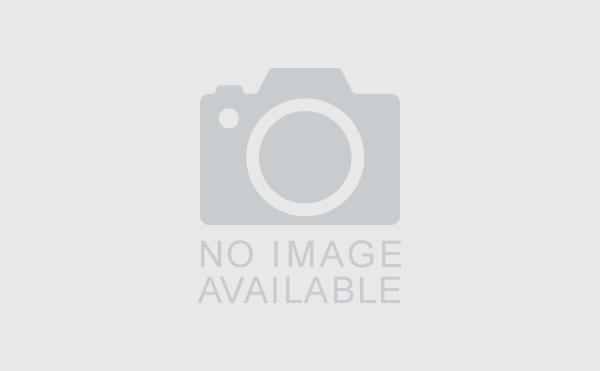「長さ」の学習~2年生算数~
市内小学校の2年生は,「長さ」の学習をひととおり終えたところでしょうか。
この「長さ」の単元では,初めて「単位」を学びます。
「長さ」の学習で出てくるのが「竹尺」です。そう,2年生になると必ず購入する,あの30cmの竹の「ものさし」です。
2年生のなかには,「単位」でも「長さの計算」でもなく,この「竹尺」に苦戦するお子さんがいます。

上の写真のプリントの赤い書き込みのようなことをするお子さんがいます。
本人は,先生が教えてくれた通りに一生懸命1cmのいくつ分かを数えているのです。ところが,1cmを区切る線を正しく見極めることが彼らにとっては視覚的に難しく,また,「1cm」という感覚も未熟なので,おかしいと感じることができないのです。
そのようなお子さんには,まず,「定規」を使って学習することを進めています。

「定規」には,目盛りに数字が書かれているので,正しい長さが一目瞭然です。1cmと,その間にあるmmの目盛りとの違いも理解しやすくなります。
プラスチック製で透明なので,線と目盛りが多少重なってしまっても測れます。
また,「定規」は,もともと線を引くための道具なので,2年生の手にも扱いやすく線も曲がらずに引けます。
定規を使って指定した長さの線をどんどん引かせて遊ぶと,1cmや5mmなどの感覚を楽しく身につけることができます。長さを測るときにも,定規を使えば簡単に正しい答えが分かって,学習を楽に=楽しく進めることができます。
そうした後に竹尺にもどると,目盛りに数字のない竹尺でも,簡単に長さを測ることができるようになっています。
「長さ」の学習であって,「竹尺」の学習ではありません。自信をもって楽しく意欲的に学習してほしいです。