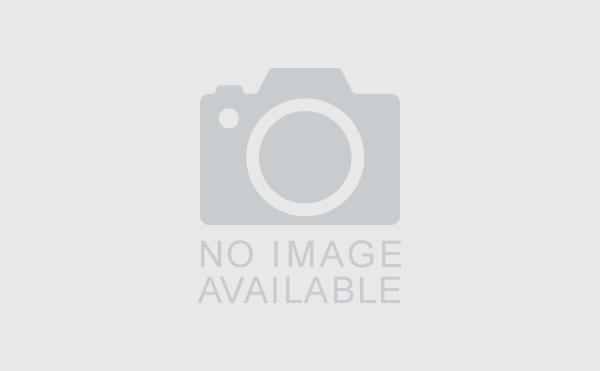かけざん九九~がんばれ2年生!
算数…発達段階に即した「学び」の大切さ
小学2年生では,いよいよ「かけざん」の学習が始まりました。
正確に パッと言えるようになるまで しっかりと覚えることが必要になってきます。
(暗記が苦手な私は,全部の段に合格したのがクラスで一番最後だったことを今でも覚えています…。)
九九を正しく速く言えるように暗記することは,とっても大変ですが,「かけざん」には,別の難しさもあります。
発達保障論の専門家のなかには,「かけざん」を2年生で学ぶのは早すぎるとおっしゃる先生もいらっしゃるくらいです。
それは,「3+4=7」のたし算だったら,
「りんご3個+りんご4個=りんご7個」のように,一つの物で考えられる計算であるところを
かけ算では,「3×4=12」が
「りんご3個ずつ×4袋分=りんご12個」と2種類の数がでてきます。
その概念を理解できるまでに発達しているかどうか…
それが,2年生だと,ぎりぎりのところだ,というのです。
数や言葉の概念が発達していないのに,機械的に計算の仕方だけを覚える学習には落とし穴があります。
「計算はできるけど,使えない子」が出てくるのです。
特に,かけ算を学習すると顕著になります。
文章問題で,「これは,たすの?ひくの?あっ,それとも,かけ算かな?」
という具合です。
国語が苦手だから読解力が無くて…とおっしゃる方もいますが,
そればかりでなく,計算の概念が理解できていない場合も多いのです。
かけ算の練習は,ぜひ,かけ算の意味を日常生活の中で確認しながら行っていってほしいと思います。
「ヨーグルト3個入りだから,3の段だね。」なんて,お買い物のなかでも沢山できそうです。