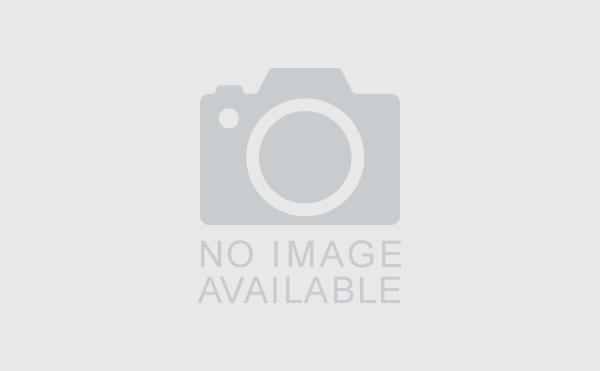入学前に,どこまでできるようにしておけばいいですか?

最近、年長児の保護者の方によく聞かれます。
小学校の運動会に招待されたり,就学時健康診断を受けたりと,小学校への入学が急に現実的に感じられるようになってくる時期ですね。
保護者の方のみならず幼稚園の先生からも度々聞かれることは,「学校からは,『自分で身の回りのことができて,自分の名前の読み書きと30くらいまでの数を数えられるように…』といわれたけれど,本当にそれだけできればいいのか?」というようなことです。
現行の学習指導要領では,小学校入学後の入門期に平仮名も10までの数も学習することになっていますから,それを入学前に学んできてくださいとは,小学校の先生はおっしゃらないと思います。
しかし,本来,発達段階からすると,子どもは4歳半頃から「自然と文字や数に興味を持ち」,入学前には「いつの間にかほとんどの平仮名や数が分かっている」と考えられています。
実際にそのようなお子さんが多く,学校の先生がおっしゃるように,入学時に自分の名前と出席番号が分かるように練習してきてくれれば,入学後に,正しい書き方で平仮名を繰り返し練習し,数の数え方や仕組みも丁寧に教えてもらうことで,子ども達は驚くほど急に,ぐうんと伸びていきます。
つまり,「できるようにしておく」というより,「(成長の過程で)できるようになっている」ことが前提の話なのです。
ところが,しばらく前から,「今の子どもは,特に低学年以下では驚くほど『分からない』『分かっていない』という子が多く見られます。」という意見が出ています(註1)。これは,算数の場合ですが,ここでは「親世代が小さいころは子どもが多く,いろんな年齢の子どもと遊ぶことで,数の概念は自由に覚えられました。でも今は違います。一つひとつ,親が教えないと覚える機会がないのです。教え込むのではなく,意識的に日常会話の中で,数についての経験をさせるのが大事ですね。」(註2)と幼少期の子どもへの関わり方の大切さが説かれています。
入学前の「素地作り」は大切だと思います。
ポイントは,日常生活の中で,無理なく(嫌いにならないように),楽しく(意欲がもてるように),ちょっとした関わりや工夫をすることで,子どもの発達に寄り添っていくことだと思います。
※(註1)(註2)ともに
「小学生の学力を伸ばす本」(2010年 宝島社)P98
杉渕鐵良「学校では教えてくれない 算数でつまずかない学習テクニック」より引用