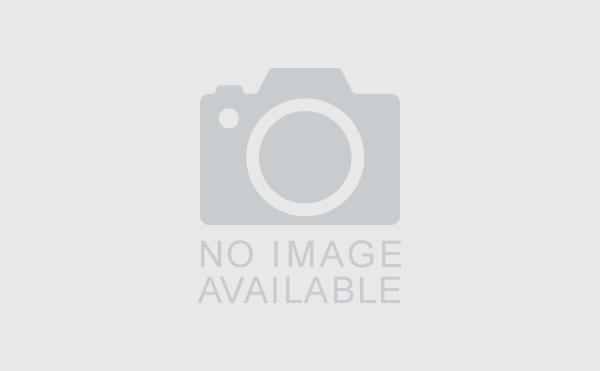長さ(小2)と角度(小4)

2年生が「長さ」、4年生が「角の大きさ」の学習に入ってきました。どちらも、初めて触れる単位(㎝、㎜、° )について学習をします。
ここで、苦労するのが、ものさし(竹尺)と分度器の使い方です。
まだ、長さの単位や角度についての感覚をつかんでいない状態なので、センチメートルの枠が分からないまま数えていたり、分度器の目盛りを反対から読んでとんでもない角度で答えていたりしても、本人は気がつきません。
そのため、「わからな~い」「にがて~!」というお子さんが出てきます。
そんなときには、まず、長さの単位や角の大きさについての感覚を高める学習を優先してみましょう。
長さの場合は、目盛りのついた透明の定規を使って問題を解いてみましょう(上の写真)。「なあんだ。かんたんじゃん!」となります。今は、見やすく色分けされていたり、子どもが片手で抑えても滑らないように加工されていたり、使いやすいように工夫された様々な定規が販売されています。お子さんに合った定規を探してみてください。
角の大きさの場合には、すでに分度器や大まかな角度が印刷されている問題で練習しましょう(下の写真)。分かりやすく簡単にできます。そして、解いていくうちに、分度器のあて方や角の大きさについても理解できるようになっていくと思います。


あくまでも「長さ」や「角の大きさ」の学習です。竹尺や分度器は、道具の一つにすぎません。
お子さんに合った道具や問題を用いて、学習を進めていきましょう。
※写真は、下記問題集より
上の写真:「算数習熟プリント 小学2年生 大判サイズ」著者:図書啓展 金井敬之・濵﨑仁詩 発行所:清風堂書店
下の写真(2枚とも):「1日10分 計算力・思考力が身につく 算数ドリル 小学4年生」著者:藤原光雄 発行所:フォーラム・A