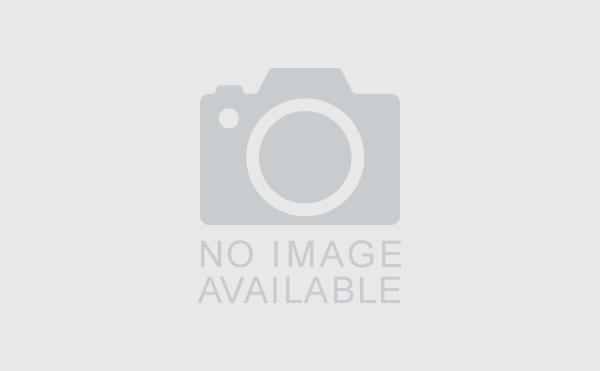とけい~小学1年生

市内の小学1年生が使用している教科書では,9月に1時間「とけい」の学習が入っています。「なんじ なんじはん」の学習です。
取り扱いが1時間程度の簡単な内容にもかかわらず,案外,ここで苦労するお子さんがみられます。「何時・何時半」の学習であるのに,例えば「10時半」を「10時6分」などと読もうとするのです。何より,学習しようとすると「時計わかんないんだよな。」などと,最初から気持ちが萎えてしまっています。これから初めて学習しようとしているのに,すでに「わからないんだよなあ。」とは? これは,早期に時計の読み方を覚えさせようとしたことが裏目に出てしまった結果かもしれません。実際に,園児の保護者から「まだ,時計が読めないんですけど…。」との相談を受けることがあります。
算数の学習は,学んだことの積み重ねだとよくいわれます。そしてその通り教科書も緻密につくられています。
例えば,時計の学習にしても
9月初旬「10よりおおきいかず」…20までの数,数直線の考え方→「12」までの数や,時計のめもりの読み方ついての理解へ
↓
9月中旬「なんじ なんじはん」(時計の短針の読み方,短針と長針の関係)
↓
1月初旬「大きなかず」…120までの数,「かずのせん」の見方→「60」までの数や,大きな目盛りの間の小さな目盛りの読み方が分かる
↓
1月中旬「なんじなんぷん」(長針の読み方,短針と長針を合わせて読む。生活に生かせるようにする。)
このように,数学的な思考力を身につけ数の世界を広げながら,時計に取り組んでいくのです。
1年生の9月の段階では,短針が8の目盛りを指していれば「8時」,8と9の半分のところにあれば「8時半」,短針が1目盛り移動する間に長針が1周することが分かれば十分で,とっても簡単なはずなのです。
ましてや,園児でしたら,日常生活の中で自然に時計にふれていれば十分に感じます。短針・長針・秒針の動きを目にして何となく時計の針の動きが分かっていたり,家を出るとき,お昼の12時,寝る時刻など,折に触れてアナログ時計やデジタル時計に目をやる習慣がついていたりすれば,時間や時刻の感覚が磨かれていくと思います。豊かな感覚を身につけておくことは,様々な学習の素地となります。
もし,早くから時計を読めるようにしておきたいときには,目盛り1つ1つに60までの数が書かれている時計も市販されているので,それを日常的に家族みんなで使うことで自然に読めるようになるのをねらってはいかがでしょうか。
まずは,苦手意識を抱かせないように配慮してほしいです。
※写真は
・教科書:大日本図書「たのしいさんすう1ねんせい」
・プリント:清風堂書店「算数習熟プリント1年」
・時計玩具:成近屋「おふろでパズル いまなんじ」